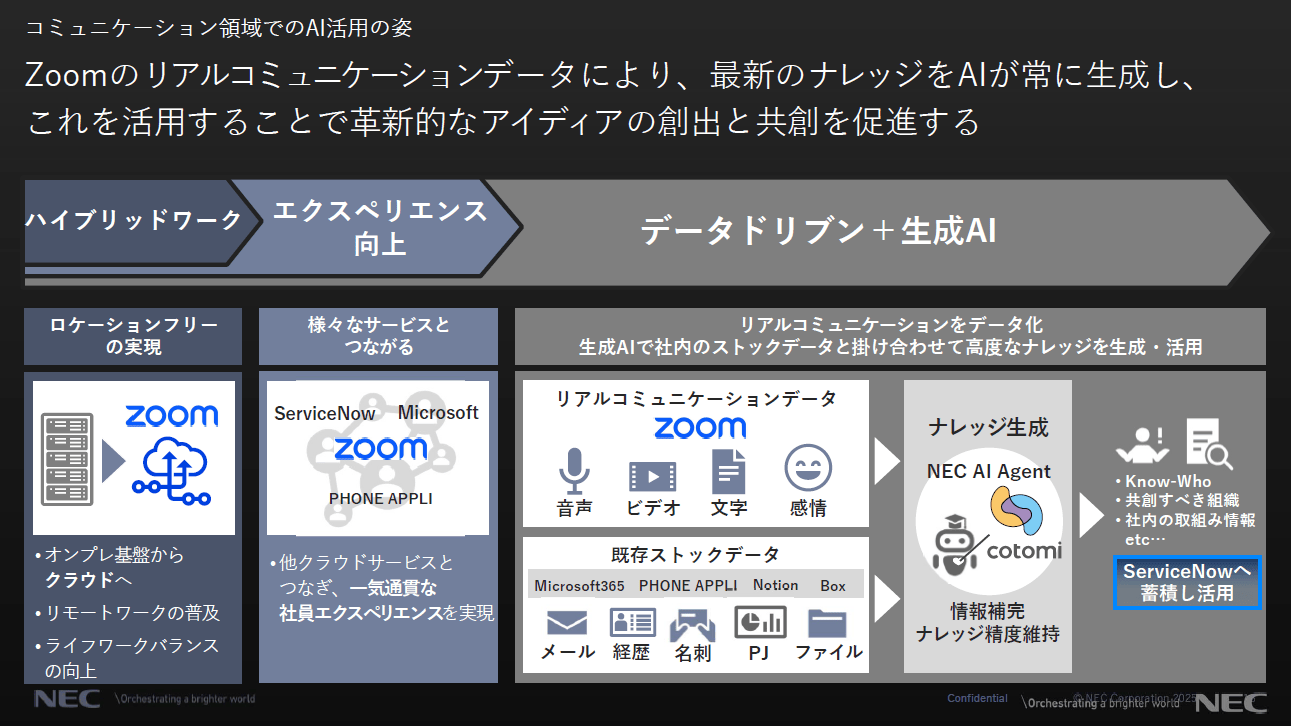人とAIが自然に協働する社会を目指して データの価値を高めていく挑戦
コスト最適化の観点でも、一番にすべきことは利用状況の可視化。リプレイスを成功させるためには、この棚卸しを徹底的にすることが急務でした。
デジタルID・
働き方DX統括部 シニア主幹 小口 和弘 氏