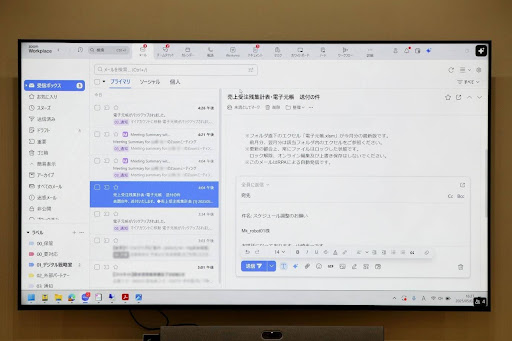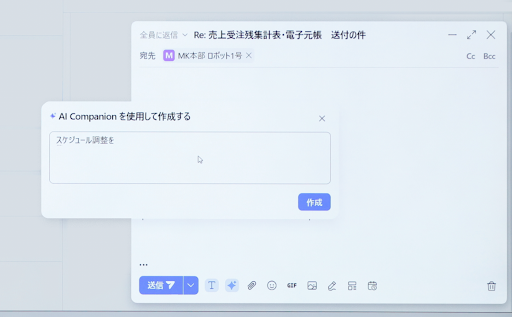同社の生産工場は「点心・デリ工場」「アイス」「菓子」「あずきファクトリー」などがあり、「点心・デリ工場」だけでも製造工程は9つのプロセスに分かれています。
広大な工場の中で、細分化された工程に分かれ、さらに早番・遅番のシフト制で24時間稼働を続けるため、当日のスケジュールや申し送り事項をタイムリーに共有するうえで、チャットは最重要ツールになっていると点心・デリ工場 工場長代理 上嶋健人氏は話します。
「常に忙しい工場内で相手の作業を止めたくないので、チャットを使うことが多いです。テキストで説明しにくいことは写真や動画を添付できますし、シフトの交代時に状況をキャッチアップするにも重宝しています」

衛生面から備品の持ち込みが制限される食品工場内で、社用スマホ1台で遜色なく機能を使えるのもメリットです。
「材料や備品の発注の確認・承認もチャットで完結できるようにワークフローを整えました。急ぎの場合は電話を使いますが、Zoomのアプリから、そのままビデオ会議や電話ができるのも便利です」
情報共有においては、Zoom Roomsのデジタルサイネージ機能(※)も活用。工場内の計4か所に設置したモニターに、作業内容や手順、注意点などを動画で解説し、映し出しています。
※ 指定した画面にあらかじめ設定したコンテンツや情報を表示できる機能。会議室や待合室に設置したモニターに、スライドショーや動画を流すような使用が想定されている。
「弊社の工場では、ブラジルやフィリピン、ベトナムなどの海外にルーツを持つ従業員も多く働いています。いかに言語の壁を越え、正確に情報共有するかは常に大きな課題。言葉やジェスチャーだけではわかりにくいところを母語の字幕をつけて伝えられる、作業しながらその場で実際の映像で確認してもらえるので、本当に重宝しています」
サイネージで動画を流す案は、現場の従業員が提案したもの。日々Zoomに親しんでいるからこそ「Zoom Roomsの機能を使えばできるのでは?」というアイデアが出てきたと言います。
コンテンツの差し替えや追加も簡単で、IT担当者に頼ることなく、上嶋氏の手元のPCでできるのも日々状況が変わる工場ではメリット。「今日必要な情報を、すぐに伝えることができています」と現場目線でDXの成果を語ります。