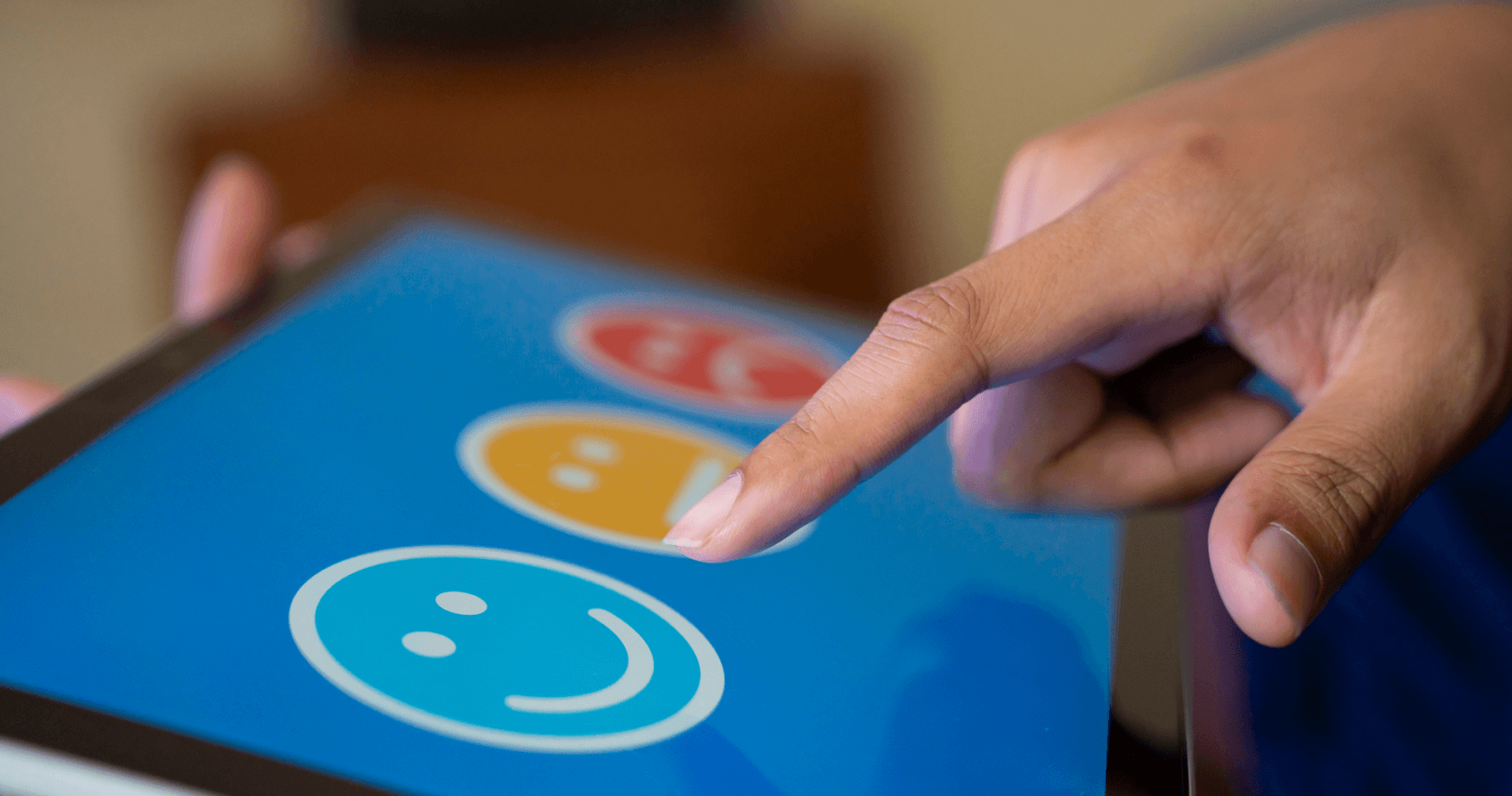
次世代の CX における成功に VoC プログラムが重要となる理由
AI 対応の Voice of the Customer(VoC)プログラムが最新の CX にとって不可欠な理由をご確認ください。Metrigy の社長である Irwin Lazar 氏が提供する実用的なインサイトを見ていきましょう。
更新日 December 20, 2021
公開日 December 20, 2021


今年は、昨年「Zoom」が流行語になって以来、Zoom が瞬く間に社会のインフラとして浸透したと言っても過言ではない飛躍の一年だったのではないでしょうか?
ZVC JAPAN株式会社(Zoom)社長 佐賀文宣に今年一年の振り返りと来年の展望について、10 の質問をしました。
Q1 – 佐賀さんにとって、2021 年はどんな一年でしたか?社是の「Delevering Happiness」、幸せは社会、そして個人に届きましたでしょうか?
一言でいうと、Zoomが社会の信頼を取り戻す事ができた大切な一年だったと思います。
つまり、急に流行ったビデオ会議の会社という去年のイメージから日本人の生活に本当に取り込まれてプラットフォームになって行くための最初の大切な年になったという訳です。具体的には、様々な企業との商談、そして国会期間中には議員会館に私自身も何度も足を運ぶなど、政府機関、大臣、議員の方々と会談し、Zoomのご提案をしました。又、大分県をはじめ地方自治体や民間企業と包括連携協定を結び、市民サービスのサポートのご提案もしました。
現在緊急事態宣言は明けましたが、解除後も尚、ビデオコミュニケーションの技術を使い、暮らしや働き方を便利にするご提案を続け、受け入れられて行った年だったと感じています。社会や個人に幸せが届けられたかというと、それはむしろユーザーの皆様が感じて下さる事、私たちは社是を追求すべく歩みを進められたと思っています。
Q2 – 特に今年、印象に残ったお客様はいらっしゃいましたか?そのお客様はどのように Zoom を活用していらっしゃいましたか?
最近増えているオフィスでお使いのお客様ですね。これまでもこういったコミュニケーションツールは使っていらしたのですが、リモートワークが進み、エンゲージメントが下がり、社員同士の結びつきも希薄になり、優秀な人材が離れて行ってしまったり、集まらなかったりしたそうです。つまりそのような経営課題を抱えているお客様が増えていて、既存のツールではエンゲージメントの改善が見られず、二重投資になるにも関わらずより性能の高いZoomを併用して課題に対処なさったのが特に印象的でした。相手の表情を見ながらコミュニケーションを継続できる、という点が評価されたと理解しています。私たちはお客様のITの課題に取り組んでいると思っていたのですが、実は、お客様の経営課題に直結していたのだと認識し、勉強になりました。
Q3 – 佐賀さんのハイブリッド型ビジネス環境は Zoom のロールモデルとして定着、むしろ更に進化中と察しますが、今年何か新しい価値観は生まれましたか?逆に無性に恋しくなった事などありましたか?
実は、弊社はまだハイブリッド環境は構築できておらず、100% リモートワークなのです。勿論 Zoom でコミュニケーションしているのですが、早くオフィスに戻りたい気持ちで一杯です。社員が同じ空気の中で一緒に汗を流せる様な環境を作りたいと切に願っており、その思いが日に日に大きくなってきています。そして、お客様が訪問したいと思える様なオフィスを構え、最新の Zoom の設備を導入し、お客様を迎える。そして私たちもハイブリッドワークを実現する事が、来年以降に持ち越した私と社員の夢です。私が恋しいのは社員ですね。
Q4 – 「 Zoom 映え」という新単語がすっかり情報社会のボキャブラリーに加わりましたが、佐賀さんや社員の皆さんが普段工夫している事などありますか?
社員は社会のイベントや季節を意識して、ひんぱんにバーチャル背景を変えています。これがアイスブレイクに最適で、会話をスムーズに始める事ができます。又逆説的ですが、社内で Zoom コミュニケーションが増えている、つまりミーティングばかりになってしまっているので、水曜日は「No internal meeting day」として、社内のミーティングを入れず集中して思索する日を設けています。これはグローバルな取り組みでもあるのですが、Zoom を日常の一部として長く使っていくために必要な工夫だと感じています。使うのではなく使わないノウハウ、それを協調して意識的に取り込む事でなかなか上手く行っていると実感しています。
Q5 – Zoom でのコミュニケーションは言語を介し、主に視覚、聴覚で図られる様に思われます。佐賀さんにおかれまして、何か特別に磨かれたコミュニケーションスキルはありますか?
私にとって「磨かれたコミュニケーションスキル」というのは少しアグレッシブに感じます。実は私が意識しているのは、自分がどんどん出て行かないという事なのです。お客様とは勿論、社内での打ち合わせでも、自分はニコニコとうなずきながら聞く様にしています。相手に安心感を与え、皆さんが豊かなコミュニケーションを図れる様、ニコニコと耳を傾ける事が私の重要な役回りだと思っています。リモートコミュニケーションはトップダウン指令型ではなく、共感型のコミュニケーションの方が有効だと日頃感じており、つまり、指令するのではなく皆さんの話し合いを引き出し、相互の共感を経て合意に導く、というのが私のスキルと言えますでしょうか...
Q6 – 皆様待ち望んでいると思いますが、リアルタイム自動翻訳機能の日本語対応は実現するでしょうか?それで、ライブ文字起こしが可能になれば、ドラえもんの「ほんやくコンニャク」が現実になる訳ですね!
既に 9 月末の Zoomtopia で発表されていますが、来年中に字幕機能が日本語対応になる予定です。話している事がリアルタイムで字幕になり、自動翻訳され、選んだ言葉で表示されるという事で、夢の世界だった「ほんやくコンニャク」は完成します!実は、Zoom はセキュリティ関係以外あまり技術買収はしないのですが、今回は世界各国の言語の翻訳技術を持っているドイツの Kites という会社を買収し、その技術を使って実現させます。日本語への翻訳精度は現段階で正直まだ良くわかりませんが、改良されて行く事と思います。先ずはリリースされる事を嬉しく思っています。
Q7 – さて、今年 10 月に導入された新サービス、Zoom Phone の評判が早速聞こえて来ておりますが...
実は正直に申し上げますと、Zoom Phone はまだお客様のニーズに充分応えられていない、つまり本丸を攻めるには至っていないのです。というのは、現在は 050 で始まる電話番号にしか対応できていないからです。来年前半早々になると思いますが、03、06 などから始まる 0ABJ 番号を提供して初めて、Zoom Phone が爆発的に普及すると想定しています。在宅勤務でも、どこにいても、会社の電話を取れます。例えば、在宅勤務で散らばって働いている方々が、まるでオフィスにいる様に、かかってくる電話にチームで順番に応答する様な事は Zoom Phone の様なクラウド PBX にしかできません。簡単に言えば、お手持ちの携帯電話で会社にかかってくる電話も取れて、電話をすれば会社からかけている事になる。コスト面でも非常に優れており、皆様がまさに必要としているサービスだと認識しています。
Q8 – 今年は東京オリンピック・パラリンピックはもとより様々なジャンルのコンサートも無観客でライブ配信がなされました。美術館や博物館のバーチャルツアーも登場しました。スポーツや文化芸術の価値が再認識された様に感じられますが、今後 Zoom は会議室からスポーツ施設やコンサート会場などエンタメ空間にも飛躍し、イノベーションをもたらしてくれるのでしょうか?
確かに、企業のコミュニケーションは様々で、会議、イベント、セミナーなど Zoom が得意としていた分野からエンタメに限らずあらゆる分野に広がって来たという実感はあります。企業、団体が一般消費者や市民とコミュニケーションするという意味ではもっと広くご支援できるポテンシャルがあり、例えば、コンタクトセンター、キオスク、銀行や役所の窓口などこれまで対面で実施されていた業務の中でZoomのビデオコミュニケーション技術が活用されて行く様になるでしょう。つまり今後、エンタメだけでなく多様な場面でイノベーションが期待されると思います。
Q9 – コロナ渦が落ち着いたら、人々は元のワークスタイルに戻ると思いますか?もしくはこのままハイブリッド型が定着するでしょうか?もしくは何か他の新たな進化を想像しますか?その場合、Zoom はどのように社会をサポートして行くのでしょうか?
大きく分けて 3 つのタイプの方々がいらっしゃると思います。1 つは元に戻りたい方。2 つ目は元に戻りたくない方。3つ目は、そもそも現場で働かざるを得なかった、つまり一度もリモートの技術を使う機会がなかった方です。実は3つ目のカテゴリーに日本人の大多数が属すると思うのです。病院勤務だったり、配達業務だったり、店舗に立つなど現場で従事なさっていた方々です。つまり、リモートワークに言及なさっているのはオフィスワーカーの一部の方々だけなのではないでしょうか、という事です。そこで、先ず 1 つ目、2 つ目のカテゴリー、オフィスワーカーの方々が戻る、戻らないに関して申し上げれば、優秀な人材を確保、つなぎ止めるためにはリモートワークという選択肢が必須になるでしょうから、ハイブリッド型は定着すると思います。次に3つ目のカテゴリー、現場で業務に取り組んでいらした方々は私たちの日常生活にとって欠かせない存在で、ビデオコミュニケーション技術をより活用して頂ける余地があると思っています。現場の仕事の 10% でも 20% でもビデオコミュニケーション技術を導入して頂く事によって、日本全体で生産性やリスク管理など安全性が向上するだろうと考えています。もしコロナ渦が収まっても、新たなパンデミックや台風や大雪など自然災害は起こり得ると想像します。その際オフィスワーカーの方々はさすがに既に学んでいらして対応できるでしょうが、この 2 年間現場に通い従事なさって来た方々がどのように対処して行くのか、今後のオンライン技術導入のご提案に Zoom の存在価値があると思っています。
Q10 – 最後に2022年の展望をお聞かせ下さい。
もっともっとインフラになって行きたいと思います。企業活動や市民活動の中で使って頂く事、そしてその企業と市民を結ぶインフラになるという事です。そのために、既存の業種別の業務フロー、サービスは世の中に沢山あるのですが、それらの中にZoomの技術を組み込んで行くというのが重要だと思っています。つまり、Zoom というロゴが出て来ない、Zoom と分からなくとも様々なサービスに組み込まれている状態を創り出すという事です。ユーザーの皆様が Zoom を使用している事を意識せずともいつの間にかビデオコミュニケーションが図られている世界を目指したいと思っています。又ビジネス全体としては、引き続き尽力し、売り上げにおいて二桁の成長を達成したいと思っています。新 2022 年、Zoom が皆さんの生活により溶け込んでいく事を願ってやみません。